はじめまして、よでぃと申すものです。
当記事では、『生きづらくも平凡な僕の人生』について、自分語りをしていこうかと思います。
長くなりますが、もしよければ、暇つぶし程度に読んでいっていただけたら幸いです。
それでは、どうぞ。
生きづらくも平凡な僕の人生
初めは、小学校5年生の頃だった。
自分は周囲に嫌われている。自分は周囲から浮いている。
明確に、あるいは被害妄想的に、そう感じるようになった。
友達だと思っていた人たちからハブられ、悪口を言われ、避けられる日々。
それでも僕は1人になることが何よりも怖くて、周囲についていこうと必死だった。
どれだけ傷つけられても、どれだけ嫌な思いをさせられても、みんなといることを選んだ。
その間違った努力こそが、いずれ自身の身を滅ぼす結果につながるとも知らずに。
王のお遊び
中学にあがり、「充実した学校生活を送るぞ」と意気込んだ僕は、早速クラス内での友達作りに励んだ。
僕が最初に声をかけたのは、ひときわ明るくて、中学一年生にしてどこかカリスマのようなオーラを放つ一人の男の子だった。
「彼と仲良くなれば、学校生活は絶対に充実したものになる!」
そう確信させるほどの人間としての魅力が、その男の子にはあった。
「はじめまして、僕よでぃ。よろしくね」
「おう、こちらこそよろしく。仲良くやろうぜ」
お互いに笑顔で挨拶を交わし、他愛もない世間話に花を咲かせた。
何を隠そう、僕は初対面の人とうまくやるのは得意なのだ。
※
きっと、初めは順調だった。
実際に彼と仲良くすることで、芋づる式に多くの人たちとつながりを持つことができた。
休み時間をみんなで一緒に過ごし、部活動見学をみんなと一緒にまわり。
順風満帆な滑り出し!最高の中学校生活がスタート!
・・・の、はずだった。
僕は初対面の人とうまくやることは得意だが、根っこは内気で人見知りな性格だ。
だんだんと“素の自分”がばれ始め、僕自身も誰とでも仲良くしようとすることに疲弊し、一人また一人と、僕のまわりから人が離れていった。
最終的に、例の彼ともテンション感が合わなくなり、僕は孤立した。
ときに皆様方、“スクールカースト”と呼ばれるものをご存じだろうか。
陽キャだとか陰キャだとかに人を区分し、暗黙の了解でランク付けが勝手に行われる、アレである。
僕は初っ端から人間関係に失敗したことで、そのスクールカーストの最底辺に位置付けられた。
一方で、最初に仲良くなったと思っていた男の子は、直に十クラスもある学年全体におけるスクールカーストの頂点に君臨する男、すなわち“王”だった。
そんな彼から言い放たれた
「なんかお前、違うわ」
という重すぎる一言が、今でも呪いのように頭の奥の方にこびりついて離れない。
中学校生活がはじまって二か月。僕へのいじめが始まった。
※
いじめは約半年ほど続いた。
王とその仲間たちは僕のことを見つけるや否や、集団で僕を取り囲み、悪口をあびせかけた。
家に帰ろうとするとニヤニヤしながらついてこられたり、誰がマンションの部屋番号を教えたのか、家のインターホンを何度も何度も鳴らされたりもした。
「もうやめて」
と懇願しても
「なにが?俺たち一緒に遊んでるだけじゃん」
と、笑って受け流された。
とはいえ、直接的な暴力や、トイレで水をぶっかけるといった、目に見えるいじめ行為はほとんどなかった。
「そんくらいならよくね?」と思う人も、中にはいるかもしれない。
正直な話、あれは“いじめ”ではなくただの“いじり”で、僕が自意識過剰なだけだったのではないかと考えてしまうこともある。
それでも、当時の僕にとっては地獄の半年間だった。
学校に行くのが怖い。
外に出ることすらも怖い。
インターホンの音が怖い。
ひそひそ話の声が聞こえてくるのが怖い。
他人が全員、僕のことをみてニヤニヤしているように見える。
みんながみんな、悪い顔をした悪魔に見える。
それ以降、僕は今でも、他人の顔をちゃんと見ることができなくなった。
※
そんな僕へのいじめも、ある日を境にぱったりとなくなった。
僕が勇気を振り絞って立ち向かったとか、正義のヒーローがさっそうと現れていじめっ子たちをこらしめてくれたとか、そんなドラマみたいな出来事が起きたわけではない。
ただ単純に、“いじめの対象”が僕から違う人へと変わっただけだ。
あくまでいじめは、王のお遊び。
僕へのいじめに飽きたから、他の人をいじめたくなった。
その気まぐれに、たまたま救われただけだったのだ。
それでも、当時の僕は、ただひたすらに安堵していた。
これでもう、怖い思いをせずに済む。
明日からは、安心して学校に通える。
もう地獄から解放されたのだと、冗談抜きで神様に感謝すらしたほどだ。
・・・僕の代わりに、“次の対象”が地獄のような思いをすることになったとも気づかずに。
僕もまた、他の人と同じ悪魔の一人だったのかもしれないと思うと、吐き気がする。
※
なにはともあれ、その後の中学校生活は比較的平穏なものだった。
僕がひたすらにおとなしくしていた甲斐もあってか、誰に目を付けられることもなく、毎日をやり過ごすことができた。
ただずっと、スクールカースト上層部に席を置く人たちの機嫌を損なわせないことに全力を注いだ。
なんとも息苦しくて、小さな格差社会の檻に閉じ込められているかのような気分だった。
だけど、大丈夫。きっと大丈夫。
生きていれば、いつかきっといいことがある。
いつかきっと。
俺のターン
中学を卒業し、高校生になった。
同じ中学出身の陽キャたちが一人もいないような、そこそこの偏差値で、あまり人気がない高校を選んだ。
そこで僕は「今度こそ充実した学校生活を・・・」と希望を抱き、高校デビューを試みた。ナカノのワックスを片手に。
結論から話すと、高校デビューは成功した。
友達はできたし、ラグビー部に入部して先輩とも仲良くなれたし、なんと初めての彼女を作ることにも成功した。
その頃は、毎日が楽しくて仕方がなかった。
遊〇王風に言うと、「俺のターン!(ドン☆)」といった感じだ。
生きていれば、いつか必ずいいことがある。
生きていれば、神様が微笑んでくれる瞬間が必ず訪れる。
僕はやっと報われた。どんな困難も、我慢して耐え続ければ希望の光が待っているのだ。
と、当時の僕は本気でそう思っていた。
しかし現実は、思い通りにはいかないからこその現実なのである。
※
高校デビューは成功した。
というのも、やはり最初の方だけの話だった。
入学してから数か月が経過したころ
「あいつ、なんか調子乗ってね?」
という陰口が、僕の耳元にまで届いた。
そして、だんだんと周囲から嫌われ、浮いた存在となり、避けられていると感じるようになった。
しかしまあ、当時の僕は調子に乗りすぎていたなと、今なら思う。
それもそのはず。中学校という石の上での三年間をおとなしく過ごした僕にとって、“程よい調子の乗り方”なんてものはわかる由もなかったのだ。
さらに僕は、集団生活に耐えきれずラグビー部も退部し、初めてできた彼女とは手もつながずに別れた(とほほ)
その後、アルバイトを始めてみたり、打ち込める趣味を探したりもしたのだが、どれも長くは続かなかった。
高校を卒業するまで、青春を謳歌している同級生たちを横目に、なにを成し遂げるわけでもない空虚な毎日を消費していくだけだった。
※
高校で時間だけは持て余していた暇人豚野郎の僕は、自分自身と向き合う機会が人一倍多かったように思う。
自分には何ができるのか。自分にはどんな価値があるのか。
自分が生まれてきた意味は?自分の人生に与えられた使命とは?
そういった自問自答を、何度も何度も繰り返した。
そして最終的にたどり着く結論は、いつだって
「自分には生きている価値がない」
というものだった。
たいそうな夢も目標もない。誰の役にも立っていない。
普通の人にできることが、僕にはできない。普通の日々を歩むための方法がわからない。
考えすぎのストレスで、大腸炎になったり、胃潰瘍になったりもした。
それでも、大丈夫。きっと大丈夫。
生きていれば、いつかきっといいことがある。
いつかきっと。いつかきっと。
異変を告げる赤いあざ
高校も無事卒業し、某MARCH大学へと進学を決めた。
キラキラとしたキャンパスライフを夢見た僕は、相も変わらず大学デビューを試みる。
その結果は・・・いうまでもないだろう。ここまで読んでくれた方なら、想像に容易いことと思う。
そう、“最初だけは”うまくいった。いつも通りだ。
しかしこの男、バカなのか。今までの人生でいったい何を学んできたのか。
学習能力がクソザコである。クソザコナメクジと言ってもいい。
・・・おい、それは言い過ぎだろう、僕のライフはもうゼロよ。
話を戻すと、最初の一か月は、入学式の日に意気投合した学部の友人たちと共に、数多のサークルの新入生歓迎会に足を運んだ。
そのなかで、僕が入部を決めたのはオールラウンドサークル。
オールラウンドサークルとは通称“オーラン”と呼ばれているもので、「色んなスポーツをやって汗を流そう!」という名目でウェイウェイするウェイサーのことである(詳しくはググってみてほしい)
はじめのうちは、とりあえずウェイウェイ言っておけばなんとかその場のノリについていけた。
しかし例のごとく、だんだんと周囲との距離感に差が開いていることに気が付いた。
そりゃそうだ。当然だ。
ギラギラのパリピオオカミの群れに、表面だけは明るく取り繕っているものの根っこは人見知り陰キャの羊が一匹迷い込んだのだ。馴染めるはずもない。
周りはあんなにも楽しそうなのに、自分だけが置いてけぼり。
それでも理想のキャンパスライフを送るべく、「今度こそは」と決意を新たに、必死になって周囲の人たちについていこうとした。
※
大学に入学し、しばらくたったある日のこと、僕は一つの異変に気が付いた。
身体中のあちこちに、“赤いあざ”のようなものができ始めていたのだ。
最初は首にそのあざができたため、友人からは
「おいおい、キスマークつけて学校くんなよ~」
なんてからかわれたりもした(もちろんキスマークなどではない)
僕自身、あまり重くとらえることもなく
「ちょっとした肌荒れだろ、すぐに治る」
と考え、特に気にしていなかった。
しかし、みるみるうちにそのあざは全身に広がっていき、さすがにおかしいと思い始めた僕は皮膚科を受診。
“アトピー性皮膚炎”だった。
アトピー性皮膚炎とは、超絶簡潔に説明すれば、身体中のあちらこちらがかゆくなる皮膚病である。
「え?かゆくなるだけ?」と思う方も少なくないだろうが、“かゆみ”のつらさはバカにできない。
患部が傷だらけになるまでかきむしり、出血どころかジュクジュクとした組織液のようなものまで染み出てくる。
シャワーを浴びる際には日焼けした直後のようなひりひりとした痛みが全身を襲い、小さな悲鳴をあげながら湯船に浸かる。
肌は赤みが目立つようになり、鏡を見ることが怖くなる。
かゆみでどうしても目が覚めてしまうため、ぐっすりと熟睡することができない。
そんな気が狂いそうになるような日々を、僕は送っていた。
それでも大学に通い続け、サークル活動への参加もやめなかった。
毎日のようにぱんぱんに予定を詰め、あまり得意ではないはずの飲み会にも積極的に足を運んだ。
「よでぃ、飲んでなくない??wowwow!!」
お酒を飲むように促すコールがきこえる。
僕はそれに偽りの笑顔でこたえ、ジョッキに注がれたビールを胃の中に流し込む(よいこはマネしないでね)
飲み会が終わり帰宅して一息つくと、アルコールで血流がよくなりすぎたためか、とても我慢することなどできないかゆみが全身を襲う。
一通り身体中をかきむしった後、痛みをこらえてお風呂に入り、温まった身体中を再びかきむしり、浅い眠りにおちていく。
※
お酒の飲みすぎに、合わない人間関係のストレスが相まって、アトピーの症状はどんどん悪化していった。
それでも僕は、誰に強制されているわけでもないのに、何かに取りつかれたかのようにサークル活動に参加し続けた。
今思えば、理想とする自分とのギャップを認めたくなかったのだろう。むしろ「いかなきゃいけない」とすら考えていたような気がする。
それほどまでに、僕は“充実した人生をおくること”に躍起になっていたのである。
しかし、どれだけ予定をぱんぱんに詰め込んでも、いつまでたっても僕の心が満たされることはなかった。
それどころか
「ここに自分の居場所はあるのだろうか」
「自分は必要とされている存在なのだろうか」
と、不安や焦りといった感情に付き纏われるようになっていった。
みんなはすごく楽しそうなのに、どうしてもそこに馴染むことができなくて、疎外感に苛まれて。
一人でいるときよりも、誰かと一緒にいるはずなのに感じる孤独の方が、ずっとずっと寂しいものなのだということを痛感した。
どうして僕は、みんなと同じように生きられないのだろう。
どうして僕は、こんなにも生きることがへたくそなのだろう。
答えの出ない問いを、頭の中で反すうする。
だけど、大丈夫、きっと大丈夫。
生きていれば、いつかきっといいことがある。
いつかきっと。いつかきっと。いつかきっと。
就活という名の悪魔の諸行
大学3年生の終わり際、僕はサークルを引退した。
それと入れ替わりになるように、就職活動という名の悪魔の諸行が始動する。
会社説明会やインターン、エントリーシートの作成に、面接の練習。
『就活』の二文字を頭に思い浮かべない日がないほどに、それは日常へと溶け込んでいった。
大学4年生になり、エントリーシートが通過した企業との面接がスタート。
当時はちょうど、コロナウイルスが最も世間を賑わせていた時期だった。
面接のほとんどがオンラインで実施され、イレギュラーな就職活動となった。
その逆風のせいか、はたまた単に自身の実力不足のせいか、僕はまったく思い通りに就活を進めることができなかった。
家の中にいるのに、スーツを着て髪型を整え、パソコンの前に座る。
「私が学生時代に力を入れて取り組んだことは・・・」
「私が御社を志望する理由は・・・」
『ガクチカ』や『志望動機』など、入念に準備してきた回答を愛想よく口にする。
しかし、まったくもって内定は出ず、お祈りメールばかりが届く。
その結果を見るたびに、僕は自分のすべてを否定されているかのような感覚に陥り、消えてしまいたくなる。
気が付けば、持ち駒が全滅。
僕は、『就活』という戦いに大敗した。
※
普通の人なら「もういちど頑張るか!」と立ち直ることができるのかもしれないが、僕にはそれができなかった。
就活のストレスでアトピーが重症化し、うつの症状まで現れ始めたのだ。
エントリーシートを書かなければいけないのに、パソコンを開く気力すら起きない。
いざパソコンを立ち上げても、頭がボーっとして働かない。
だんだんと、ご飯を食べるのも、お風呂に入るのも、布団から出ることでさえ、億劫に感じるようになった。
それでも、かゆみだけは延々と襲ってくる。
かゆい、つらい、苦しい、かゆい。
どうして自分だけがこんな目に。
どうして、どうしてどうしてどうしてどうして
僕は布団の中で身体中をバリバリとかきむしりながら、家族に聞こえないように声を押し殺して泣いた。
自分が生きている意味が、本当にわからなかった。
死んでしまいたいと、本気で思った。
それでも、大丈夫。きっと大丈夫。
生きていれば、いつかきっといいことがある。
いつかきっと。いつかきっと。いつかきっと。いつかき
※
・・・“いつか”って、いったい、いつなんだろう。
“いつかきっと”は訪れない
それから数か月、僕はまさに“生ける屍”と化した。
一日の大半を、布団の中で過ごす日々。
布団から出るのは、ご飯を食べるときとトイレにいくとき、それから数日おきにお風呂に入るときくらいだった。
なにもする気力が起きない。
なにをしていても楽しくない。
ネガティブな考え事が止まらない。
“生きている”というよりは“耐えている”という表現の方が、当時の僕の日常にはしっくりくる。
それでも、眠っている間だけは、嫌なことを忘れられる。
眠りについたまま、もう二度と目が覚めなければいいのに。
※
ある日、洗面所の鏡で自分の顔をみたときに、僕はショックを通り越して笑ってしまった。
そこに映っていたのは、伸び散らかした髭と髪の毛、死んだ魚のような眼、そして掻きすぎてかさぶただらけになり、赤く腫れあがった顔面。
まるで人間のものとは思えないような、化け物じみた容姿だった。
「・・・醜い」
僕の口から、自身を罵倒する声が漏れる。
「醜い、醜い、醜い、醜い」
自分の額を、鏡に何度も何度も打ち付ける。
「醜い!醜い!!醜い!!!醜い!!!!」
その声を聞きつけた母親が洗面所に駆け込んできて、僕を抱きしめるようにして抑え込む。
自分の実の息子が、発狂しながら鏡に頭をぶつけている姿をみた母親は、いったいどんな気持ちだったのだろう。
※
僕を心配した母親から「いちど病院にいってみたらどうか」と提案を受けた。
僕はその提案を受け入れ、隣駅にあるメンタルクリニックを受診。
心のお医者さんから、どんな症状なのかと尋ねられ、一つずつ答える。
なにもする気力が起きないこと。
なにをしていても楽しくないこと。
ぐっすりと眠れない日が続いていること。
どうしようもなく気分が落ち込み、死んでしまいたいと思うこと。
症状を話しているうちに、僕は情けなくも泣いてしまった。
その後いくつかの質問に答え、担当の精神科医から
「うつ病ですね」
と、診断結果を告げられる。
それを聞いた僕は、意外にもあまりショックは受けなかった。
むしろ、なにも頑張れないのは自分が怠けていたわけではなく、うつの症状だったのだと知り、安堵の念が広がったほどだ。
それにしても、今までこれといって悪いこともせず、なるべく他人に迷惑をかけないように真面目に生きてきた結果がこれか。
「生きていれば、いつかきっといいことがある」なんて、嘘っぱちじゃないか。
“いつかきっと”は訪れない。
「いつかきっといいことがある」の、“いつかきっと”は訪れない。
僕はずっと
僕はメンタルクリニックから帰宅し、母に告げる。
「お母さん、僕、うつ病だった」
母はそれを聞いて、ささやくような声で
「そっか」
とつぶやく。
数秒の沈黙。
いたたまれなくなった僕は、自室に向かおうと足を動かす。
すると
「ずっと、頑張って生きてきたんだね」
母が口を開き、僕の耳に言葉を届ける。
「気づいてあげられなくて、ごめんね」
その言葉が、僕の胸の中にやけにストンと落ちてきたのを、今でも鮮明に覚えている。
ずっと頑張って生きてきた・・・
僕はずっと・・・僕はずっと・・・
僕はその場に立ち尽くし、だんだんと目頭が熱くなっていくのを感じる。
そうか・・・
そうだったのか・・・
僕はずっと、頑張って生きてきたのか・・・
だからずっと息苦しくて、心が疲れてばかりいたのか・・・
気が付けば、僕は再び泣いていた。
壊れた水道管のように、あふれ出る涙が止まらなかった。
僕はずっと、見栄を張り、背伸びをして、明るい自分を演じてきた。
みんなと同じように生きるために。みんなに受け入れてもらえるように。
だけど、誰からも嫌われないように努めているうちに、気が付けば自分で自分のことが大嫌いになっていた。
僕はずっと・・・僕はずっと・・・
心の中で、先ほど母が僕にくれた言葉を、今度は自分で自分自身に向かって語りかける。
「ずっと、頑張って生きてきたんだね」
「気づいてあげられなくて、ごめんね」
心を覆っていた雲が涙と一緒に流れ落ちていき、少しだけ晴れやかな気分が広がった。
※
はたから見れば、僕の人生はごく平凡なものなのだと思う。
なにか秀でた才能があるわけでもなく、芸術やスポーツで優れた結果を残しているわけでもない。
それでも僕は、凡人な自分なりに、毎日を一生懸命に生き抜いてきた。
普通になれない生きづらさを抱えながらも、醜くも必死になってもがいてきたのだ。
その頑張りを、僕はいちどすべて手放してみた。
理想の自分を、未来への期待を、何者かになるための努力を。
すると、心がスッと軽くなるのを感じた。
人が生きづらさを感じる原因は、“頑張りが足りないから”ではない。
むしろ真実はその逆で、“頑張りすぎてしまうから”つらくなるのだと、僕は悟った。
ところで、『諦める』という言葉はマイナスな意味合いで使われることがほとんどだが、本来は『明らかに見る』というポジティブな意味合いをもつ言葉らしい。
心がいっぱいいっぱいになってしまっているとき、いちど頑張ることをやめ、現状を明らかにすること。
それにより、冷静さを取り戻し、物事を俯瞰して見ることができるようになり、より穏やかな心持で日々を歩めるようになるのだという。
頑張ることはとても素敵なことだが、ときには諦めて開き直って、肩の力を抜いてみることも大切なのかもしれない。
大切なこと
それから僕の人生は、少しずつ好転していった。
アトピーもうつ病も完治、就職してすぐに出世、恋人ができてハワイで結婚式をあげ、子供もつくって休日は家族で旅行に出かける。
・・・なんていうのは夢物語。ただの僕の妄想である。
実際は、アトピーは薬を使ってなんとか症状が落ち着き、うつ病はある程度は寛解、仕事はすぐには見つからず、もちろん恋人はいない。それが現実だ。
それでも、確かに変わったものが一つだけある。
それは、僕の“心の在り方”だ。
自身の心の在り方一つで、世界は美しくも醜くもなるものなのだと、僕は学んだ。
※
かつての僕は、ずっと間違った頑張り方をし続けてしまっていたのだなと、今ならわかる。
他人と自分を比較して、他人にどう思われるかばかり気にして、何者かになりたくて、“どうしたいか”よりも“どうすべきか”に縛られて。
けれど、ただがむしゃらに頑張って、漠然と将来の自分に希望を託したところで、それが叶うことはほとんどない。
あるいは、もし叶うことがあったとしても、ないものねだりを続けている限り、心が満たされる日はいつまでたってもやってこない。
大切なのは、“今”を生きること。
今この瞬間、あるがままの現実を受け入れ、今ある幸せに目を向けることだ。
「いつかきっといいことがある」の“いつかきっと”は訪れない。
だからこそ、“今の自分の本心”に耳を傾けてあげるのだ。
幸せは、どんな些細なものでもいい。
むしろ、些細なものだからこそいい。
ご飯がおいしい、アニメが面白い、推しが尊い、天気がよくて気持ちがいい。
そんな小さな幸せを積み重ねていくことで、塵も積もれば山となり、豊かな人生が実現していく。
それこそが、今の僕にとっての幸福の形である。
※
もちろん、大きな夢や希望を抱くことも決して悪いことではない。
だけど、足元に咲く小さな花の美しさも、見落としてしまってはもったいない。
そんな小さな幸せに気づくためには、やはり“心の余裕”が重要となる。
ときに諦め、肩の力を抜き、全身全霊で脱力すること。
のんびりと、穏やかな心持で、人生の流れに身を任せること。
人生は、前に進むことだけがすべてではない。
立ち止まるときがあってもいいし、下を向くときがあってもいい。
頑張ることに疲れたら、頑張ることをやめたっていい。
周りに縛られず、自分のペースで、ゆっくりと。
焦らず、無理せず、生き急がず。
自分の人生を、自分自身の足で歩んでいきたいと思う。
さいごに
以上で、僕の人生についての自分語りは終了です。
普段は『X(Twitter)』にて、日々の生きづらさのモヤモヤを言語化する活動をしています。
僕の投稿を読んでくれた人がそれに共感し、少しでも楽な心持ちになってくれたらいいな、なんて願いを込めて発信しております。
フォローはこちらから。もうすでにフォローしてくださっている方は、いつもありがとうございます。
なにはともあれ、皆様とともに脱力した人生を歩むことができる日を、心から楽しみにしております。
それでは、今回はこの辺で。
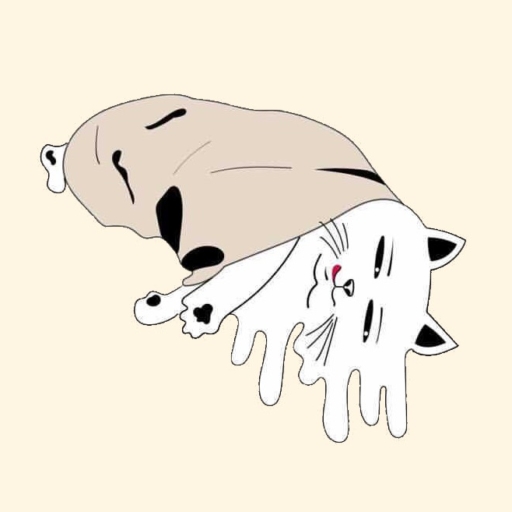 だるねこさん
だるねこさんアディオス


コメント